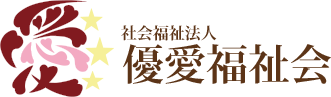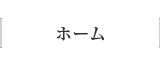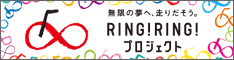ホーム > ブログ
2024/03/04
施設長のつぶやき~趣味・嗜好品の取り扱いに関する議論②~
機動戦士ガンダムSEED FREEDOMが公開されて一カ月以上経ちました。
この日はまだ公開後10日ほどだったと思いますが…
予想はしていましたが凄い状況です。
しかしパンフレットぐらいは劇場で観た人は必ず買えるようなシステムになる事を
切に願うばかりですね。
しかしこの日観に行ったのはSEEDではなく…
こちら。
迫力満点で非常に面白かったです。
ただし結構残酷な描写もありますで、苦手な方は注意して下さい。
あらすじとネタバレと感想はこちら。
それでは前回の続きです。
指定基準では「可能な限り居宅における生活の復帰を念頭に置いて
入浴、排泄、食事等の介助、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他日常生活上の世話
機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行なうことにより
入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを
目指すものであり、常にその運営の向上に努めなければならないこと」とされています。
指定基準上はあくまで在宅復帰を支援するための自立支援を目標にするようにとなっています。
在宅復帰に関しては現実的にはなかなか厳しい目標であると思います。
しかし在宅復帰が厳しいからといって、
特養に入ったから自由気ままに何もしなくて良いという訳でもありません。
飲酒によって入浴、排泄、食事等がままならないようでは話になりません。
通常の食事が食べられるのに嗜好品ばかり優先し
結果栄養バランスが著しく崩れていく事も良い状態とは言えません。
「健康で文化的な最低限度の生活」とはよく生活保護法で耳にする文言であります。
しかし何も生活保護法に限らず
「健康で文化的な最低限度の生活」を送る事は国民が等しく有する権利であり
ノーマライゼーションの理念とも合致します。
国民が等しく有する権利であれば当然特養で生活される方々の権利でもあります。
その権利を有する方に支援を行う立場の我々には
その権利を行使して貰えるようにする責任や義務があります。
その観点からある程度
施設における通常のサービス提供に支障が出る状況が続く場合は本氏に話をし
納得して頂けるように支援の道筋を創る義務が支援者にはあるでしょう。
ここで肝心なのはこのような状況が続く場合ということです。
仮にたまたま1回飲酒によって入浴出来なかったり排泄を失敗したりしたからと言って
「はい、禁酒~」は適切ではないでしょう。
仮に少し間食が過ぎたから今日の夕飯は少し控えめにしよう等があっても
直ちに不適切とは言えません。
だって自宅で暮らす我々でもそんな日はあるでしょう。
だから④はあえて「通常のサービス提供に著しい支障がない」と考えたところです。
冒頭の特養は「家」であり「生活の場」であり「社会」と考えた場合
稀に通常のサービス提供に支障があったからと言って
全てを制限するのは不適切と言えます。
④の条件によってある程度の制約を行なっている施設は多いと思います。
しかし何の根拠も持たず
「特養とはこういうものだ」「施設に入ったのだからルールに従うべきだ」
という考え方のもと、何でもかんでも制限するのは好ましくありません。
どうしても制限せざるを得ないのであれば
先述の①~④のような事をしっかり議論したうえで本氏に納得して貰う事が必要でしょう。
それがエビデンスというものです。
ハッキリした根拠があればそれは歴とした適切な支援となるでしょう。
しかし逆に言えば根拠もないのに一律に制限をかけるというのは不適切ということです。
趣味嗜好品に制限をかければある意味、皆が同じような環境になります。
それを平等といえば聞こえは良いかもしれません。
しかし一律な制限というものは真の平等などではなくそれはまさに悪平等であり
重大な権利侵害に該当する事は頭に入れておく必要があると思います。