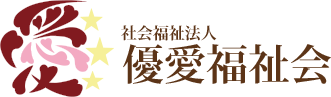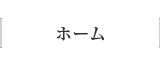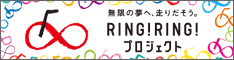ホーム > ブログ
2022/09/20
施設長のつぶやき~事故を検証する意味・ヒヤリハット報告書と事故報告書の観点から②~
台風14号が上陸しました。
大阪では大きな被害はなかったようですが
九州地方や広島では死者や行方不明者が出ているそうで
お亡くなりになった方にはご冥福をお祈りすると共に、行方不明の方の一刻も早い救出と
被害に遭われた方々の日常生活が取り戻せる事を心よりお祈り致します。
それでは前回の続きです。
先述の食レク中のむせ込みのケースでいえば
食レクでは普段召し上がって頂けない食事を提供する訳ですから当然通常の食事より
誤嚥、窒息等の危険は高まります。
このようなケースがあった時に一番悪い解決策が
「このようなメニューは危険だから提供しない」という結論と思います。
これでは事故の検証ではなくただの排除です。
排除してしまうのではなく、どのようにすれば安全に食レクを行なえるかを
前向きに検討する事が事故の検証である事はいうまでもありません。
しかしこの排除の理論がしばしば介護施設では起こります。
しかもこの排除の理論はトップダウンで行われるというよりも
実際に事故が起こった際に管理職などから必要以上に叱責された事により現場が萎縮し
「もう止めておこう」という気持ちになるのです。
トップダウンであれば安全管理の基、やるもやらないも管理者の責任になるので
ある意味仕方ない事もあります。
私にしてももし真夏にお寿司イベントをすると言われれば延期を検討する事もありますし
今、流しそうめん等感染の危険が高まるイベントが計画されれば中止を指示するでしょう。
しかし先述のような事故後の叱責による無言の圧力は一番現場の士気が下がりますし
結果、一番大切な利用者の楽しみというパフォーマンスが低下します。
管理職が必要以上に叱責し介護現場を委縮させておいてそれでパフォーマンスが低下すれば
「イベント中止は現場が決めた事、パフォーマンスの低下は現場の責任だ」というようでは
管理職としてあまりにも無責任です。
このような事から私は事故の検証には大きく分けて二つの意味があると思っています。
一つは次に同じような事故を起こさないために利用者の心身機能や介護方法等を検討する事
つまり利用者の安心、安全を守る事です。
そしてもう一つが「事故を起こしてしまった」と責任を感じている介護職員に
失いかけている自信を取り戻させ、介護の仕事を続けていく勇気を与える事です。
(しかしもちろん、介護技術が未熟な職員には技術の向上を求める必要はありますし
いい加減な介護をしていた場合には大いに反省して頂く必要はあります)
そのためには介護職員だけではなくその他の専門職が叱責ではなく的確なアドバイスをしたり
管理職が声をかけたりする事が求められます。
自信や勇気をもって貰うという意味においてはヒヤリハットで鋭い視点や良い気付きがあった場合
称賛する事も必要です。
褒められて伸びない人間などいません。
しかしヒヤリハットはともかく
事故の場合は利用者、家族に多大な迷惑をおかけするのも事実です。
その点は施設全体として反省する必要はあるでしょう。
しかし反省だけで終わってはいけません。
利用者の安全、安心を守るために次は同じ事をしないとさらに自己研鑽し介護技術を磨き
より成長していく必要があります。
事故を起こしてしまった事で萎縮しこの業界を去っていく人も確かにいるでしょう。
しかし事故を経験しさらに成長する人も多くいます。
そのような成長していく人にならなければなりません。
それがこの業界に身を置く者の責任ではないでしょうか。
ヒヤリハット報告書も事故報告書も罰を与えるものでは決してありません。
後ろを向くためにあるのではなく、前を向くためにある事を忘れないでほしいと思います。