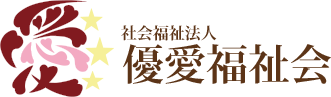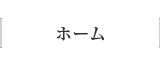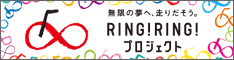ホーム > ブログ
2022/04/08
施設長のつぶやき~組織創りについて考える②~
本日は入学式のようですね。
一律に今日なのか学校や地域によって違うのかは知りませんが
出勤時に多くの親子を見かけました。
この春新しい学校に入学される方々の中にも、この業界で働くために
高校、専門学校、大学に入学される方々が多くおられると思います。
国家資格等は簡単に取得できるものではありませんが、ぜひ数年後には
専門資格を得て、この業界に飛び込んで頂きたいと思います。
そういえば、今年の介護福祉士の国家試験、当施設からは4名受験し
4名とも合格という快挙でした!(^^)!
素晴らしい!おめでとうございます(/・ω・)/
それでは前回の続きです。
「②帰属意識は低いが能力が高い職員」に関してはどうでしょうか。
私は仕事とは総合力と思っています。介護現場を例にすると
例えばパット交換が早く正確であれば、仕事が出来る、能力が高いと思われがちです。
確かにそのように評される側面もあると思います。
しかしパット交換が早くて正確というのはあくまで
その人を評価するファクターの一つに過ぎないのではないかと思うのです。
仮にパット交換が早くて正確でも、毎回毎回組織や周囲の人間を悪くいう職員がいたら
それは組織にとって不要な職員です。
私からすればそれは「仕事が出来る人」などではなく、ただ「ケアの早い人」に過ぎません。
しかしこのようにただケアが早い、効率が良い事だけをもって
「あの人、仕事は出来るんだけどな」と言ってしまっている事はないでしょうか。
実はこれはとても危険な事なのです。
もし言葉だけでも「仕事は出来る」と言ってしまうと
組織にとって不要な人物でも組織に必要な人物と解釈してしまう危険があるのです。
ですので、私はこの業界においては「帰属意識は低いが能力が高い職員」などは
存在しないのではないかと思うのです(あくまで自分の今までの経験からです)。
残念ながら当施設にも過去にこのような職員が存在しました。
そこそこの役職に就いていた職員で、役職者の立場を利用し
「介護現場の職員の話を聞いてあげないと」という名目で
自分から積極的に介護現場の職員に話かけていました。
どこの職場でも事務方・ソーシャルワーカーと介護現場
もしくは違うユニット同士というのは
職種の違い、部署の違いでどうしても意見を違えるものです。
そのような意見の違い、ある意味溝を埋めるのが役職者の仕事なのですが
その職員は相談に乗る振りをしながら
組織(とりわけ管理者、ソーシャルワーカー)の悪口を吹聴し、煽り
溝を埋めるどころか深め、介護職員のやる気を低下させた挙句
退職に追い込むような行為を繰り返していました。
その後、様々な裏工作が明るみになった事で
その事を厳しく指摘、指導した結果その職員は退職していきました。
そしてその職員が退職してから施設の雰囲気が一変したことを強く感じました。
その職員もそこそこの役職に就いていた事から
ある一面の能力には秀でたものもあったのでしょう。
しかし仕事を総合力と考えた場合、仮に一面に秀でた能力があったとしても
帰属意識が低く、組織を混乱させる職員は決して仕事が出来る有能な職員とは言えず
組織には必要ありません(もちろん都度、指導し改善を求める過程は必要ですが)。
長くなったので続きは次回にします。