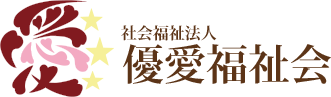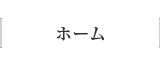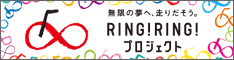ホーム > ブログ
2022/03/06
施設長のつぶやき~社会福祉の「観」と「感」と「勘」を考える~
こんにちは、施設長の田原です。
今回はのっけからカンカンカンカンといった感じですが…
まぁふざけている訳ではないので、まじめに社会福祉の「観」と「感」と「勘」を
考えてみたいと思います。
この業界に限らず、自分がその道のプロフェッショナルとして勤務している以上
その道の「観」をお持ちと思います。
この業界でいえば「福祉観」や「介護観」(以後、福祉観で統一)と表現されるものと思います。
一人一人がこの福祉観を持ち、お互いに意見交換し、良い所を吸収しあって高めていく作業が
良い施設創りに欠かせません。
もちろん自分の福祉観を他人に押し付ける事は厳禁です。
それが役職者や介護支援専門員等なら尚更です。
(管理職が利用者ファーストを実行するために必要な事を考える参照)。
私の福祉観で言えば、バイスティックの7原則を基に利用者にも家族にも職員にも
接する事を基本とし、具体的な行動、考え方としては
「利用者」ではなく「人」というものがあります。
利用者をお客様という考えのもとに「利用者様」と呼ぶ事に異論はありません。
しかしあまりに「利用者」として一括りにしてしまうと、一番大切な「人としての暮らし」を
支援できなくなる危険性があると思うのです。
よくある「利用者はこのような事をしてはならない」とか
「施設に入ったのだからこうしなければならない」という論理です。
以前にも論じた内容ですが、確かに施設に入った以上ある程度のルールはあります。
しかし一人の人間がそこで暮らしている事に関して、我々と何の変わりもありません。
まずその視点が必要です。
また自分の福祉観を持つ事や職場の同僚、他事業所の職員、研修で出会った方々等と
福祉観の共有を行なう事も重要ですが、世間一般の「福祉観」がどうなっているのかを
把握する感性を持つ事も重要です。
例えば私が初めて勤めた医療法人のデイサービス・デイケアでは転倒事故を恐れて自由な歩行等を
させないようにしていましたが、今はそんな事をしている介護施設はないでしょう。
いくら自分の福祉観が「転倒事故ゼロ」で、その具体的な行動、考え方が
「利用者は自由に歩かせない」だったとしても、今の福祉観でそんな道理は通用しません。
上記は極端な例かもしれませんが、このように今の福祉観がどう動いているのかを
確認しておかないと世間から取り残された閉鎖的な施設になってしまう危険があるのです。
つまり自らの「福祉観」を持ちながら、常に福祉の動向を感ずる能力「福祉感」も
また重要な能力と言えるのです。
長くなったので続きは次回にします。