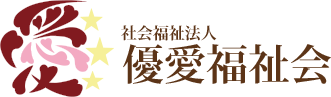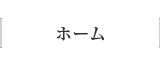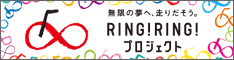ホーム > ブログ
2022/01/08
施設長のつぶやき~管理職が利用者ファーストを実行するために必要な事を考える②~
前回の続きです。
一つの例を出します。私の知っているグループホームで過去にあった出来事です。
そこのグルーホームの施設長は、介護福祉士と介護支援専門員の資格を有し
1ユニットのケアプランは自ら作成、もう一つのユニットのケアプランは計画作成担当者に
任せるものの、当然管理はしていました。
介護経験も長く、医療の知識にも明るく、まさに歴戦の介護職員と言える方でした。
私も別事業所に勤めながらも、何回も介護方法や介護観について相談した経験がありました。
利用者思いで、看取り期で入浴が難しくなってきた利用者の清拭を自ら行うのは当然
人手不足の際には夜勤にも入られており、本当にパワフルな方でした。
しかしそんな完璧に思える施設長にも一つ大きな欠点がありました。
それはあまりに知識も技術も経験もあり、また利用者思いでケアプランも担当していた事から
その施設長の考え=施設の考えになってしまっていたのです。つまり利用者に寄り添えていても
職員に寄り添えていなかったのです。
利用者にさえ寄り添えていれば良い、利用者の事だけを考えていれば良いという考えの方も
おられるでしょう。
しかしいくら優秀な方でも一人出来る事には限界があります。
管理職が目指すケアを管理職の思いだけで利用者に提供してしまうと
管理職の思いに現場の職員が付いてくる事が出来ず、管理職、現場の職員双方が
ギクシャクする結果になります。
ましてあまりの知識、技術、経験、資格等がある管理職が強く意見を言うと
現場にいる職員は言葉を返す事も出来なくなります。
ここで考えて頂きたいのは、デイサービスなどほぼ毎日管理職がいて
常に管理職が現場に入っているような事業所ならまだマシな方なのですが
我々のような入所施設になってくると管理職が常に現場にいる訳ではありません。
ましてユニット職員ではない管理職は余計に現場にいませんし、夜勤帯なら尚更です。
実際に現場にいない人の意見が優先される事ほど危険な事はないのです。
長くなったので続きは次回にします。